はじめに
ビットコインに代表される「仮想通貨」と「暗号資産」という二つの言葉を耳にする機会が増えています。同じものを指しているようでいて、なぜ二つの呼び方があるのでしょうか?本記事では、これらの用語の違い、名称変更の経緯、法律上の取り扱い、さらには国際的な動向について詳しく解説します。ビットコインやイーサリアムといった暗号技術を活用したデジタル資産について理解を深めたい方にとって参考となる内容です。
「仮想通貨」から「暗号資産」へ:名称変更の経緯
当初の「仮想通貨」という呼称
ビットコインが2009年に誕生して以来、こうしたブロックチェーン技術を基盤とするデジタル通貨は日本では長らく「仮想通貨」と呼ばれてきました。2017年4月に施行された改正資金決済法では、法律上も「仮想通貨」という名称が使用されていました。これにより、ビットコインなどは法的に認められた存在となり、日本は世界に先駆けて仮想通貨に関する法整備を行った国として注目されました。
名称変更の背景と理由
しかし、2018年に入ると、「仮想通貨」から「暗号資産」への名称変更の動きが始まります。この主な理由は以下の通りです:
- 国際的な用語統一の流れ:G20などの国際会議では「crypto-assets(暗号資産)」という表現が主流となっていました。
- 「通貨」という言葉の誤解を防ぐため:「仮想通貨」という名称は、それが法定通貨と同等の機能や信頼性を持つという誤解を招く可能性がありました。
- 投機的側面の強調:ビットコインなどは決済手段としてよりも、投資や資産運用の対象として利用される傾向が強まっていました。
このような背景から、金融庁は2018年12月に「仮想通貨」から「暗号資産」への呼称変更の方針を打ち出しました。そして2019年5月に改正資金決済法が成立し、2020年5月から法律上も正式に「暗号資産」という名称が使用されるようになりました。
法律上の「仮想通貨」と「暗号資産」の定義
定義の変更点
法律上の定義も微妙に変更されています。改正前の資金決済法では、「仮想通貨」は以下のように定義されていました:
- 物品の購入やサービスの提供に対する対価の支払いに使用でき、不特定の者に対して譲渡できるもの
- 電子的に記録され、管理されるもの
- 法定通貨または法定通貨建ての資産ではないもの
改正後の「暗号資産」の定義では、基本的な枠組みは維持されつつも、より厳密な表現となり、特に「財産的価値」という概念が明確に含まれるようになりました。また、セキュリティトークンのような金融商品としての性質を持つデジタル資産は、「暗号資産」ではなく金融商品取引法の規制対象となることが明確化されました。
法規制の変更点
名称変更に伴い、規制面でもいくつかの変更がありました:
- 顧客資産の管理強化:暗号資産交換業者は顧客の暗号資産の大部分をコールドウォレット(インターネットに接続されていない環境)で管理することが義務付けられました。
- 広告規制の強化:過度な利益を強調する広告が規制されるようになりました。
- 取引時確認の厳格化:マネーロンダリング対策として、顧客の本人確認手続きがより厳格になりました。
これらの規制強化は、2018年のコインチェックハッキング事件など、仮想通貨交換所のセキュリティ問題が顕在化したことを受けたものでした。
「仮想通貨」と「暗号資産」の実質的な違い
技術的な違いはない
重要なのは、「仮想通貨」から「暗号資産」への名称変更は、その技術や仕組み自体を変えるものではないという点です。ビットコインやイーサリアムなどの基本的な機能や特性は変わっていません。あくまで呼び方と法的な位置づけが変更されただけです。
認識や扱いの違い
しかし、名称変更によって以下のような認識の変化が生じています:
- 通貨としての側面より資産としての側面の強調:「暗号資産」という名称は、これらが法定通貨と同等ではなく、価値変動を伴う投資対象であることを明確にしています。
- リスク認識の向上:新しい名称への変更は、これらのデジタル資産に関連するリスクに対する認識を高める効果がありました。
- 国際的整合性の向上:国際機関や他国の規制当局との協調がしやすくなりました。
国際的な動向と各国の呼称
各国・地域の呼称の違い
世界各国では様々な呼称が使われています:
- 欧州連合(EU):主に「crypto-assets(暗号資産)」を使用
- アメリカ:「virtual currency(仮想通貨)」「cryptocurrency(暗号通貨)」「digital assets(デジタル資産)」など、複数の呼称が混在
- 中国:以前は「虚拟货币(仮想通貨)」としていたが、規制強化後は「虚拟资产(仮想資産)」も使用
- 韓国:「가상자산(仮想資産)」という呼称を使用
国際的な規制調和への動き
G20やFATF(金融活動作業部会)などの国際機関は、各国の規制の調和を図るために「crypto-assets」という用語を採用し、共通の規制枠組みの策定を進めています。日本の「暗号資産」への名称変更も、こうした国際的な流れに沿ったものといえます。
一般利用者にとっての影響と注意点
日常生活での呼称
一般的な会話や報道では、依然として「仮想通貨」という言葉も広く使われています。特に暗号資産に馴染みのない層には「仮想通貨」の方がイメージしやすいという面もあります。公的文書や金融機関の文書では「暗号資産」が使われることが多くなっていますが、両方の用語が混在している状況です。
投資家や利用者の心構え
名称に関わらず、暗号資産への投資や利用に際しては以下の点に注意することが重要です:
- 高いボラティリティ(価格変動性):暗号資産は価格が大きく変動する特性があります。
- セキュリティリスク:ウォレット(電子財布)の管理やパスワード管理など、自己責任の部分が大きいです。
- 規制環境の変化:各国の規制は進化し続けており、常に最新の情報を把握することが重要です。
まとめ
「仮想通貨」から「暗号資産」への名称変更は、単なる呼称の問題ではなく、これらのデジタル資産の法的位置づけや社会的認識の変化を反映したものです。技術的な違いはなく、同じものを指していますが、「資産」としての性質を強調することで、過度な期待や誤解を防ぐ意図があります。
国際的な規制の調和という観点からも、「暗号資産」という呼称への統一は意義があるものです。しかし一般的な認知度では「仮想通貨」という言葉も依然として広く使われており、しばらくは両方の名称が並存する状況が続くでしょう。
利用者としては、名称よりもその特性やリスクをしっかりと理解し、責任ある利用を心がけることが何よりも重要です。暗号資産の世界は技術の進化とともに変化し続けており、その呼称も今後さらに変わる可能性があります。
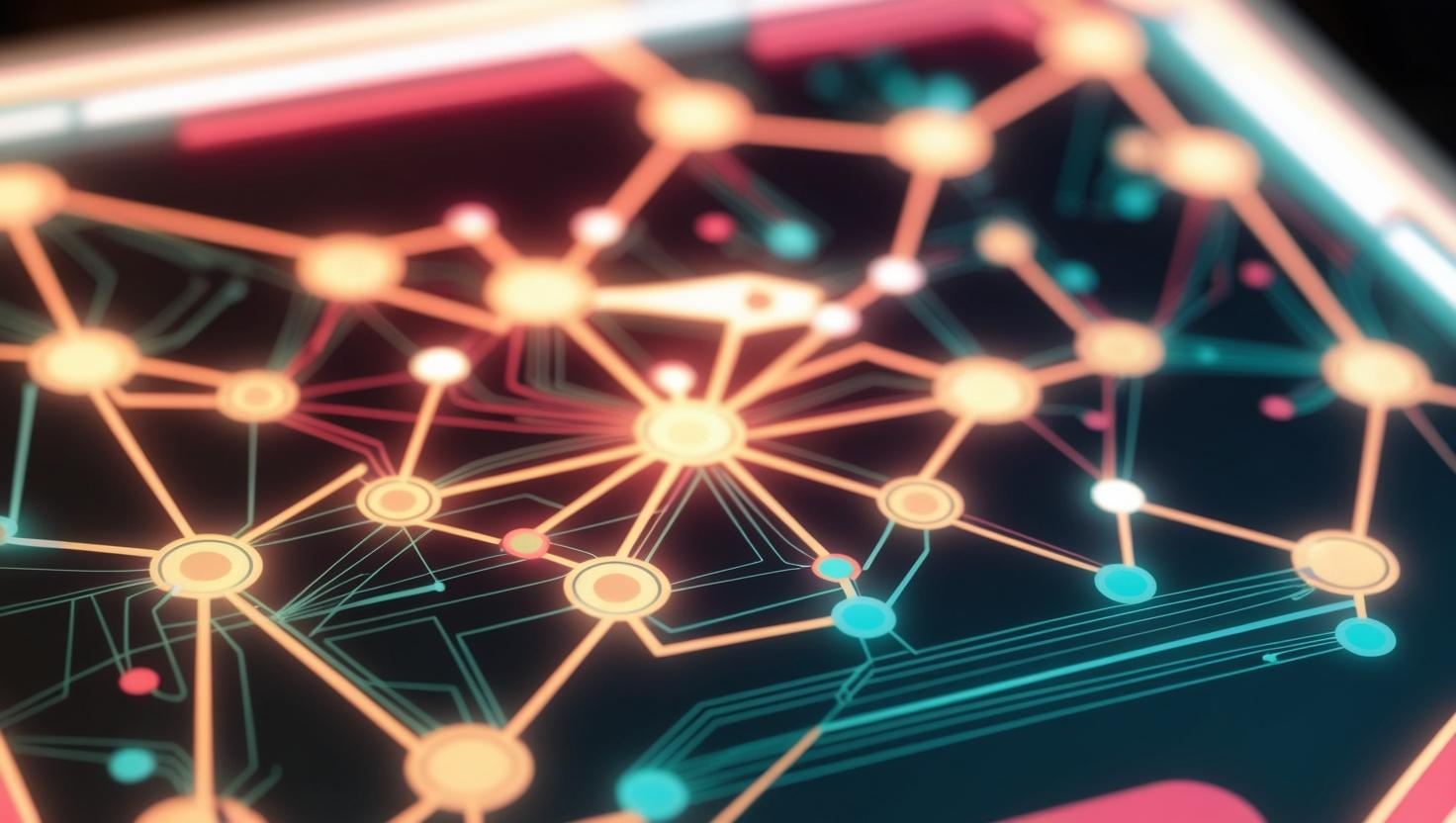


コメント